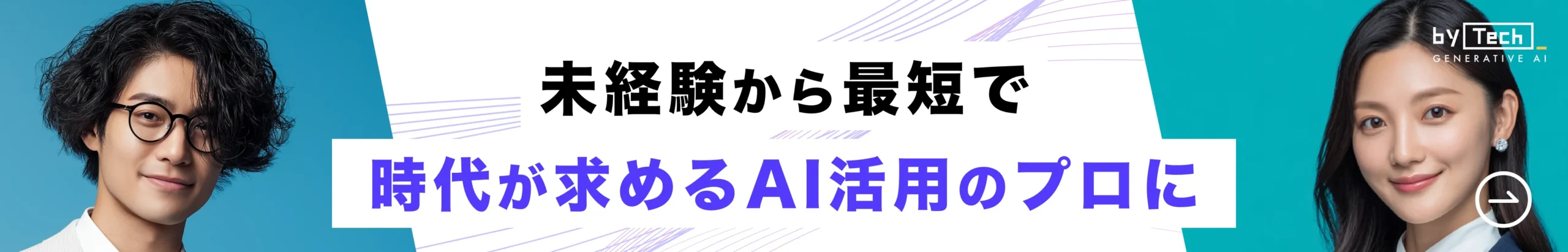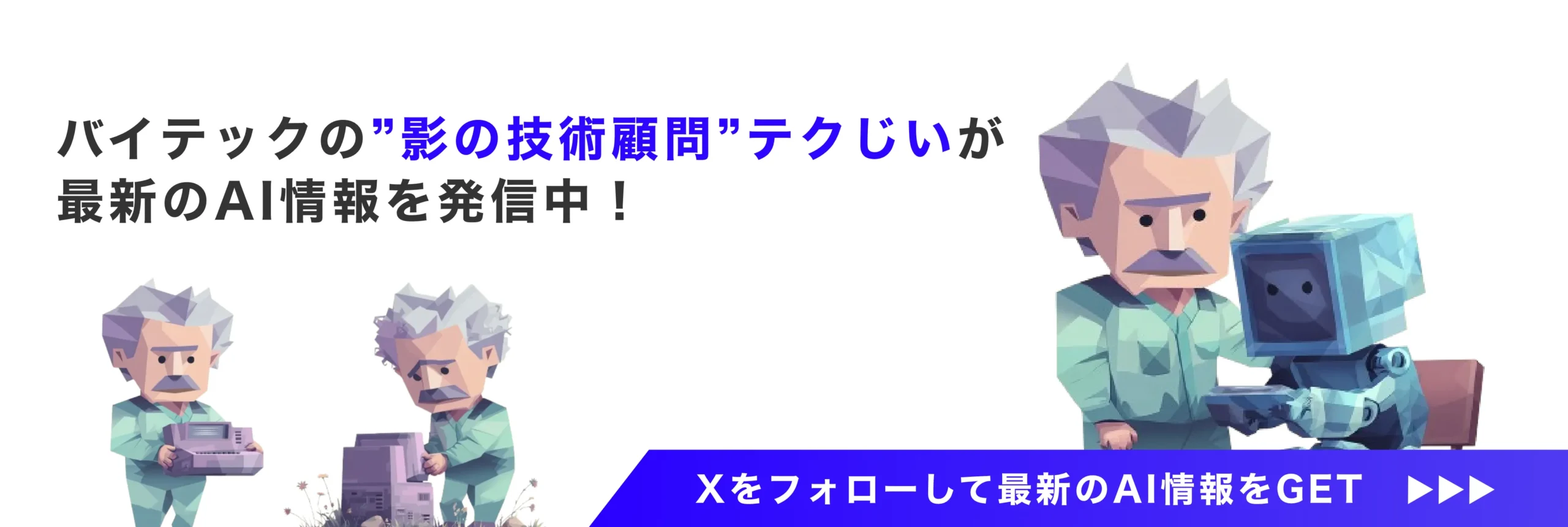業務自動化やAI活用の重要性が高まる中、注目を集めているのが「n8n」と「Dify」です。n8nは多彩なクラウドサービスをノーコードで連携させ、反復業務を効率化できるオープンソース基盤です。
一方Difyは、LLMを活用したアプリ開発に特化し、チャットボットやFAQシステムを短期間で構築できます。本記事では両者の違いを6つの視点で整理し、特徴や強みを比較するとともに、連携によって実現できるAI自動化の可能性についても解説いたします。
関連記事:Difyとは|利用のメリット・デメリットや料金、使い方について
そもそも「n8n」とは?

n8nは、ノーコードで業務自動化を実現できるオープンソースのワークフローツールです。クラウド版とセルフホスト版の2つの利用形態があり、個人の検証から企業の本格運用まで幅広く対応します。
使い方もシンプルで、ドラッグ&ドロップ操作でワークフローを構築可能です。料金プランや導入時の注意点も整理しておくと、選択がスムーズになります。
| 項目 | 詳細 |
| 特徴 | ・クラウド/セルフホスト両対応 ・2,000以上のテンプレートで即利用可 ・ノーコード操作+JavaScriptで高度な処理も可 能 ・外部サービスとの柔軟なAPI連携に強み |
| 使い方 | ・「Create Workflow」で新規作成 ・トリガーノード(Webhook、Cronなど)を設 定 ・処理ノードをドラッグ&ドロップで追加 ・Slack通知やGoogle Sheets記録などを自動化 ・保存・実行後に「Activate」で本番運用可能 |
| 料金 | ・セルフホスト版は無料(サーバー維持費のみ) ・Cloud版:無料枠200回/月 - Basic:$20〜/月(1人利用、小規模向け) - Pro:$50〜/月(高実行数+監視機能あり) - Enterprise:大規模組織向け、要問い合わせ |
| 注意点 | ・セルフホストはDockerやセキュリティ設定に知 識が必要 ・Cloud版は無料枠が限定的で商用利用には有料 必須 ・複雑なフローは習得に時間がかかる日本語情報 が少なく英語ドキュメント中心 |
上記のように、n8nは「手軽に始められるクラウド版」と「自由度の高いセルフホスト版」を備え、柔軟性と拡張性に優れた自動化基盤といえるでしょう。
関連記事:n8nとは?利用手順やメリット・デメリット、活用事例を紹介
【6つの視点】Difyとn8nの違い

Difyとn8nを比べるには、まずそれぞれの役割と特徴を理解しておくことが重要です。n8nは日常業務の繰り返し処理やデータ連携を効率化する自動化ツールであり、幅広いAPI統合に強みを持ちます。
対してDifyは、生成AIやLLMを活用したアプリ開発を得意とし、チャットボットやFAQシステムの構築に適しています。本章では、Dify・n8nの2つを6つの視点から整理しましょう。
使用目的
Difyとn8nは、目的が大きく異なります。Difyは大規模言語モデルを活用したアプリ開発に特化し、短期間でエージェントやRAGパイプラインを構築できる点が特徴です。
一方n8nは、業務プロセスやSaaS連携の自動化に強く、視覚的なUIを使って複雑な処理を直感的に組み立てられます。
| 項目 | Dify | n8n |
| メインとなる目的 | 生成AIアプリ開発・運用 | SaaS/API自動化・バックオフィス効率化 |
| 得意とする領域 | プロンプト管理・RAG・エージェント | 1,000以上のノードで統合処理 |
| 想定するユーザー | AI開発者・プロンプトエンジニア | エンジニア・データ担当チーム |
新しいAIサービスの立ち上げを目指すならDifyが有利であり、既存業務の効率化を重視する場合はn8nが適しているといえるでしょう。
主要機能
Difyは、生成AIを中心としたアプリ開発に必要な機能を幅広く揃えています。プロンプトの管理やRAGパイプラインの統合、さらにエージェント構築までをGUI上で扱えるため、専門的な知識がなくても高度な仕組みを短時間で実装できます。
一方n8nは、ノードベースのUIを採用し、ドラッグ&ドロップでループや分岐を設定可能です。1,000以上の外部サービス統合に対応し、PythonやJavaScriptを組み合わせることで柔軟な自動化も実現できます。
| 機能項目 | Dify | n8n |
| コア機能 | プロンプト管理・RAG・エージェント | ノードUI・分岐・ループ制御 |
| 外部連携 | LLMやナレッジベース統合 | 1,000以上のSaaS/API統合 |
| 拡張性 | GUIで高度なAI機能を統合 | Python/JSでカスタム可能 |
高度なAI機能を簡単に扱いたい場合はDifyが有利であり、多彩なサービスを連携させて柔軟な自動化を行いたいケースではn8nの方が効果を発揮できるでしょう。
アーキテクチャ・デプロイ
Difyは、セルフホストとクラウドの両方に対応しています。
セルフホストでは、docker-composeで起動でき、データベースやUIまで含めて一括で立ち上げられるのが特徴です。クラウド版では従量課金制を採用し、チームや企業向けにはVPCデプロイやプラグイン配信も可能です。
対してn8nは、DockerやKubernetesを使った柔軟なセルフホストに対応し、実行数やワークフロー数の制限がありません。さらにn8n Cloudでは月間実行数に応じた複数プランが用意されており、用途に合わせた選択ができます。
| 項目 | Dify | n8n |
| セルフホスト | docker-composeで簡単起動 | Docker/Kubernetes/単一バイナリ |
| クラウド版 | 従量課金・Enterprise契約あり | Starter/Proなどプラン制 |
| 特徴 | RAG・Agent・UIを一括展開 | 実行数・ワークフロー無制限 |
迅速にAI環境を立ち上げたい場合はDifyが便利であり、自由度の高い運用を求める場面ではn8nが選ばれる傾向があります。
料金面
Difyとn8nは、いずれもオープンソースとして提供されており、セルフホスト環境なら基本的に無料で利用可能です。ただし、クラウド版の料金体系には違いがあります。
Difyは、トークン数に基づく従量課金を採用し、無料枠では月3万トークンまで利用可能です。有料プランは月額49ドルからで、ユーザー数や利用可能トークン量が拡張されます。
一方n8nは、クラウド試用で500実行が無償となり、有料版はStarterで月額20ドルから始められます。商用利用に制限がなく、セルフホストであれば実行数に上限はありません。
| 項目 | Dify | n8n |
| 無料枠 | 月3万トークン・3つのApp | 500実行まで |
| 有料プラン | 月49ドル〜(Team) | 月20ドル〜(Starter) |
| セルフホスト | 無料(インフラ費のみ) | 無料(Apache 2.0) |
AIの利用量に応じて柔軟に拡張したいならDifyが向き、固定費を抑えて安定的に自動化を進めたい場合はn8nが適しているでしょう。
応用・拡張力
Difyは、AI開発に特化した環境を提供しており、LangChain互換の仕組みやエージェント構築を活かして応用範囲を広げられます。急速にGitHubのスター数を伸ばしており、AI分野での注目度の高さが伺えます。
対してn8nは、自動化の世界で長年活用されてきた実績があり、追加ノードによる機能拡張が容易です。さらにユーザーコミュニティの活発さが特徴で、フォーラムや動画解説を通じて事例が継続的に共有されています。
上記経緯から、Difyは先進的なAI活用を後押しし、n8nは業務効率化を支える基盤として強みを発揮するでしょう。
| 項目 | Dify | n8n |
| GitHub Star | 20k+ | 40k+ |
| コミュニティ | AI開発者が中心に増加 | 長年の実績と活発な交流 |
| 拡張性 | LangChain互換プラグイン | サードパーティノード導入 |
優位性
Difyとn8nは、得意とする領域が異なり、それぞれの利用シーンで強みが際立っています。Difyは、RAGやエージェントをGUI上で直感的に扱えるため、AIを基盤としたサービス開発を効率的に進められます。
n8nは、1,000以上のノードを備え、外部サービス統合や業務自動化に優れた柔軟性を発揮し、セルフホスト環境で実行数の制限がなく、コストを抑えた運用が可能です。
両者を比較すると、AI中心のアプリ構築にはDifyが適し、既存のシステム効率化やSaaS連携にはn8nがより効果を上げるといえるでしょう。
| 観点 | Difyが有利 | n8nが有利 |
| RAG/Agent開発 | GUIで統合・監視が容易 | ノードで実装可能だが手動設定が多い |
| 実行コスト | LLM推論を内部で最適化 | Self-hostで無制限に利用可能 |
| コード拡張 | LangChain互換プラグイン | JavaScript / Python対応 |
Difyとn8nの連携について

AIを業務に取り入れる際には、単体で利用するよりも複数のサービスを組み合わせたほうが大きな成果を期待できます。Difyは、生成AIを直感的に活用できる開発基盤であり、n8nは幅広いクラウドサービスをつなぎ自動化を実現するハブとして機能します。
両者を組み合わせることで、AIが持つ高度な処理力と自動化の柔軟性を同時に引き出すことが可能です。以下では役割分担、活用シナリオ、接続方法、設計要素、運用時の工夫について順を追ってご紹介いたします。
Difyとn8nの連携における役割
Difyは、大規模言語モデルを活用したアプリケーションをノーコードで開発できるプラットフォームであり、専門知識を持たない方でも直感的に扱える点が強みです。文章生成、要約、感情分析、情報抽出といった自然言語処理を幅広くカバーし、業務やサービスに合わせた高度な処理を実現できます。
また、プロンプトの設定やナレッジベースの活用によって、独自のデータを学習させたカスタムAIを簡単に作成できるため、社内FAQや商品マニュアルを取り込んだ自社専用チャットボットの構築も可能です。さらに、クラウド環境を前提にした設計でありながら、ユーザーが自在に拡張・運用できる柔軟性を持っている点も評価されています。
一方、n8nはクラウドサービス同士を統合し、データの流れを管理する自動化基盤として機能します。両者を組み合わせることで、Difyが担う知識処理をn8nが橋渡しし、適切なタイミングでの活用が可能です。
たとえばLINE連携では、Difyがユーザーからの問い合わせを理解して回答を作成し、n8nが全体の処理フローを制御しながらLINEへ返答します。両者の役割分担により、効率的で円滑な顧客対応を実現が可能です。
ノーコードAI自動化による多様な活用シナリオ
Dify、n8n、LINEを組み合わせることで、顧客対応や営業支援を幅広く自動化できます。問い合わせ処理の効率化、即時応答による顧客満足度の向上、統一された情報提供、販売促進、データ活用などの効果を得られます。
主な活用例を整理すると以下のとおりです。
- CRM連携による対応時間の短縮
- FAQ処理の自動化による人員負担の軽減
- 24時間対応による顧客利便性の向上
- 商品ページ誘導やクーポン送付による販売促進
- 会話履歴の自動保存によるマーケティング活用
上記の仕組みにより、業務効率と顧客体験の両面で成果を上げることが可能です。
Difyとn8n間のデータフローと接続方法
両サービスの連携は、WebhookとAPI呼び出しが中心となります。Difyでイベントが発生すると、Webhookを通じてn8nにデータが送信され、n8nがワークフローを起動いたします。
逆に、n8nからDifyにAPIリクエストを送り、AI処理を依頼する流れも実現可能です。たとえば、LINEユーザーが送信したメッセージをWebhook経由でn8nが受け取り、その内容をDifyに渡して応答を生成し、再びn8nが結果をLINEに返送いたします。
双方向の仕組みにより、リアルタイムでシームレスな処理が可能です。
- Difyでイベント発生 → Webhook経由でn8nへ送信
- n8nが受信し、ワークフローを起動
- n8nがDifyへAPIリクエストを送信
- DifyがAI処理を実行し応答を返す
- n8nが結果をLINEへ返送
統合ワークフロー設計の主要な構成要素
LINEとDifyをn8nで統合する際には、複数の構成要素を組み合わせて全体の流れを設計することが求められます。ワークフローの精度や安定性を高めるためには、それぞれの役割を理解し、適切に組み合わせることが重要です。
主な要素を整理すると、以下のとおりです。
| 構成要素 | 機能 | 補足説明 |
| Webhookノード | LINEからのイベント受信 | ユーザーのメッセージや操作をトリガーとして取り込み、処理の起点となります。 |
| 条件分岐ノード | 必要なイベントの選別 | 友だち追加やブロックなどの通知をふるい分け、対象となる「メッセージイベント」だけを処理します。 |
| HTTPリクエストノード | Difyへのリクエスト送信 | 受け取ったテキストをDifyのAIへ渡し、回答や要約といった結果を取得します。 |
| 応答送信ノード | ユーザーへの返信処理 | 取得したAIの応答をLINE公式アカウントからユーザーに返す役割を担います。 即時返信やプッシュ送信に対応します。 |
| データ保存・通知ノード | 履歴の蓄積や担当者への通知 | やり取りをデータベースやスプレッドシートに保存したり、Slackなどへ通知して人間の担当者につなぐ補助的な処理を行います。 |
上記の要素を適切に組み合わせることで、AIの回答を即座に返すシンプルなフローから、会話ログを分析・蓄積してマーケティングに活かす高度なフローまで幅広く構築できます。統合設計の工夫次第で、応答速度の改善、顧客体験の向上、業務負担の削減を同時に実現できる点が大きな強みです。
連携システムの構築・運用時の留意点とベストプラクティス
安定した運用を行うためには、いくつかの配慮が必要です。APIキーやトークンなどの機密情報は安全に管理し、Webhookの設定は重複を避けて一意に設定する必要があります。
また、エラー発生時のフォールバック処理を準備し、ユーザーに丁寧な案内を返す仕組みを整えることが重要です。LINEへの返信はテキストに加えてスタンプやカルーセルなどを用いることで、体験価値を高められます。
さらに、送信制限やトークン有効期限といったAPIの仕様を踏まえた設計を行うことが、安定的なシステム運用につながるでしょう。
まとめ
n8nとDifyは、いずれもノーコードで利用できる点が共通していますが、得意とする領域は大きく異なります。n8nはSaaSやAPIの統合を中心に業務効率化を支える一方で、Difyは生成AIを核としたアプリ開発を強みとしています。
両者を比較することで導入の目的に合わせた最適な選択が可能になり、さらに連携させればAI処理と自動化を融合した新たなワークフローの構築が可能です。適切な活用により、顧客対応の質向上と業務の効率化を同時に実現できるでしょう。