Difyとは|利用のメリット・デメリットや料金、使い方について
近年、生成AIはビジネスから教育まで幅広い分野で活用が広がっていますが、実際に導入を進めようとすると「開発の難しさ」や「高いコスト」が障壁となるケースが目立ちます。
導入ハードルを下げる存在として広がりを見せているのが、専門知識を必要とせず直感的に扱えるDifyです。ノーコードでアプリを構築でき、日本語対応や無料プランといった柔軟な仕組みにより、多くの利用者にとって始めやすい環境を提供しています。
さらに作成したアプリを公開・共有でき、外部ツールと連携して活用範囲を広げられる点も魅力です。
本記事では、Difyの特徴や料金体系、メリットとデメリット、利用手順までを整理し、導入検討時の参考となる情報をまとめました。
DifyとはどのようなAIか

AIを活用して新しいサービスやアプリを作りたいと考えても、専門知識が壁となり実現を諦める人は少なくありません。Difyはそうした課題を解消するために設計されたツールです。
Difyは、複雑なプログラミングを行わずに生成AIを構築できる仕組みを備えています。
テキストや画像などを生み出す生成AIをノーコードで作成でき、さらにRAG(Retrieval-Aufmented Generation)エンジンを利用して高度なLLM(Large Language Model)アプリケーションも効率的に編成が可能です。
専門的なエンジニアを確保できない状況でも、目的に応じたAIアプリを柔軟に実装できるようになるでしょう。
Difyの主な特徴
Difyは、生成AIの利活用を後押しするために設計されたプラットフォームであり、幅広い機能を備えています。直感的な操作性によって初心者でも扱いやすく、同時に専門的なワークフローや高度な応用にも対応できる柔軟さが魅力です。
ビジネスシーンでは業務効率化や顧客対応の強化に役立ち、開発の現場では試作から本格導入までスムーズに進められます。利便性と拡張性を両立している点が、多くの利用者から支持される理由といえるでしょう。
以下に主要な特徴を整理しました。
| 特徴 | 内容 |
| 使いやすさ | ドラッグ&ドロップで直感的に操作でき、マニュアルやサポートも充実している |
| 豊富なAIモデル連携 | OpenAIなどのモデルと容易に統合でき、NLPや画像認識など業務に特化したモデルを利用可能 |
| RAGの活用 | 検索と生成を組み合わせ、正確性と関連性の高い情報を提供できる |
| 組み込みツール | データ前処理や学習・評価を効率化するツール群が用意されている |
| 無料利用 | 基本機能を備えた無料プランから始められ、段階的に有料プランへ移行できる |
| 商用利用 | OSSとして提供されており商用利用が可能だが、一部はライセンス申請が必要 |
| オンプレミス対応 | 自社サーバーに導入でき、セキュリティやデータ管理面で有利に運用できる |
Difyは、初心者が安心して導入できる一方で、専門的なニーズにも応えられる柔軟性を持っています。
導入規模や利用環境に合わせて活用範囲を広げられる点が、多くの利用者に支持される理由といえるでしょう。
Difyの機能・作成できるもの
Difyは、ノーコードで幅広いAIアプリケーションを設計できる点に大きな強みを持っています。専門的なプログラミング知識を必要とせず、直感的な操作で多様なアプリを構築できるため、初心者から開発経験者まで幅広く活用可能です。
ビジネス現場における業務効率化や顧客対応の自動化だけでなく、教育分野での学習支援や研究用途に至るまで、多様なシーンに柔軟に対応できるのも特徴です。
活用範囲が広いため、利用目的に応じて最適なアプリをすぐに形にできる点は、多くのユーザーにとって大きなメリットといえるでしょう。
以下に、主な機能と作成可能なアプリケーションを表で整理しました。
| 機能・アプリケーション | 内容 |
| チャットボット構築 | 問い合わせ対応や社内サポートを自動化し、24時間稼働による顧客満足度向上や担当者の負担軽減を実現できる |
| テキスト生成アプリ | 記事・ニュースレター・商品説明などの制作を自動化し、SEO最適化や定型文の大量生成に有用 |
| 画像生成アプリ | Stable DiffusionやDALL·Eと連携し、指示テキストからイラストや写真を生成できる仕組みを開発可能 |
| 分析・要約ツール | ニュース記事や学術論文を短時間で要約・分析し、効率的な情報収集や研究活動を支援できる |
Difyは、チャットや文章作成、画像生成から情報分析まで幅広い領域に対応できる万能性を備えています。
導入目的に応じたアプリケーションを素早く開発できる点が、実務での大きな価値につながるでしょう。
Difyと混在しやすいツール
Difyと同じく、ノーコードやローコードでAIアプリや業務自動化を実現できるプラットフォームは数多く登場しています。
プログラミング知識を持たなくても扱える点や、既存のツールとの連携によって効率化を図れる点が共通の特徴です。
中でも利用者から注目を集めている代表的なサービスを5つ取り上げ、機能や特徴を比較しやすいように表にまとめました。
用途や目的に応じて最適な選択肢を検討する際の参考になります。
| ツール名 | 特徴 |
| GPTs | ChatGPTをカスタマイズし、GPT Storeで共有や収益化が可能 |
| Langchain | 複数のAIモデルを統合し、効率的にアプリを開発できるフレームワーク |
| n8n | オープンソースのローコード自動化ツールで業務効率化に有用 |
| Zapier | 約5000以上のアプリ連携が可能なノーコード自動化ツール |
| Coze | ドラッグ&ドロップでチャットボットを構築でき、初心者も扱いやすい |
Difyは、多機能な生成AI構築に強みがありますが、他のツールもそれぞれ独自の分野で役立ちます。
用途や目的に応じて選択肢を比較することが重要です。
Difyを利用する4つのメリット

Difyは、ノーコードで生成AIを構築できる利便性を備えており、専門的なプログラミング知識を持たない利用者でも直感的に操作できる点が大きな特徴です。
日本語に対応しているため、言語の壁を意識せずスムーズに学習を進められ、導入コストを抑えられることも強みといえます。
また、無料プランから気軽に利用を開始できるだけでなく、開発したアプリを短時間で公開できる仕組みも整っています。
自然言語処理や画像認識など専門性の高い分野にも柔軟に応用可能であり、幅広い用途に対応できる点が魅力です。
| メリット | 内容 |
| 日本語対応 | 言語の壁を意識せず利用可能 |
| 無料利用 | 無料プランから導入できる |
| 公開機能 | アプリを短時間で公開可能 |
| 応用力 | NLPや画像認識にも対応可能 |
日本語に対応している
Difyは、日本語を扱える点が強みです。
英語ベースのツールは操作に負担がかかりますが、母語で利用できるため直感的に扱えます。結果として、国内利用者も安心して導入できます。
無料で利用できる
Difyの導入コストを抑えたい場合は、基本機能を無料で試せます。高額なライセンス料が不要なため、予算が限られる企業や個人でも利用可能です。
初期投資を抑えつつ、AIの可能性を実際に体験できる点が評価されています。
作成したアプリは簡単に公開できる
開発後の共有方法がシンプルな点もDifyの利点です。結論として作成したアプリは短時間で公開できます。
配布手段としては、以下が代表的です。
[aside type=”boader”]- Webサイト掲載
- SNSでのシェア
- メールによる配布
迅速な共有により改善のための意見も集めやすく、開発サイクルを効率化できます。
専門性の高いアプリも開発できる
高度な技術領域への応用力もDifyの特長です。結論として専門分野に特化したアプリ開発を容易に行えます。
自然言語処理や画像認識など本来難易度の高い分野でも、ノーコードで実装が可能です。結果として専門知識を持たない開発者も実務に役立つ高度なアプリを提供できます。
Dify利用に注意したい3つのデメリット

利便性が高いDifyですが、導入にあたっては見落としてはならない制約も存在します。
たとえば、機密情報を扱う際のセキュリティ管理や、特定の利用形態で必要となる商用ライセンスの条件、さらには無料プランに設けられた利用回数やメッセージ数の制限といった要素です。
制約があるのを理解せずに導入を進めてしまうと、期待していた効率化や業務改善の効果が十分に得られない可能性があります。安心して活用するためには、リスクや制約を事前に把握し、自社の利用目的や体制に合わせた適切な運用準備を行うことが不可欠です。
以下で示す3つのポイントを確認することが、失敗を防ぐための第一歩となります。
| 注意点 | 内容 |
| 情報漏えいリスク | 機密データを扱う際のセキュリティ管理が必須 |
| 商用ライセンス | 一部の利用形態では追加ライセンスが必要 |
| 無料プランの制限 | 回数やメッセージ数に上限あり |
機密情報の漏えいリスクがある
Difyを業務で利用する際には、情報流出の可能性を考慮する必要があるでしょう。外部連携が容易な点は強みですが、権限管理やログ保存先の確認を怠ると危険が高まります。
誤操作を防ぐためにセキュリティ体制を整備し、データを扱う際は適切な制御を徹底することが必要です。
商用ライセンスが必要なケースもある
Difyの用途によっては追加の商用ライセンスが必須となります。Dify自体はOSSとして利用可能ですが、モデルやAPIによっては提供元が制約を設けています。
運用を始める前に条件を精査し、対象範囲を理解することが不可欠です。契約内容を把握せずに導入すれば、予期せぬ制限に直面する恐れがあります。
無料プランには回数制限がある
Difyの無料プランSANDBOXは、本格利用するには不向きといえるでしょう。
Sandboxでは開発回数やメッセージ数に上限があります。
試用段階では十分ですが、業務で継続的に活用する場合には制限が支障となります。有料プランを検討する判断が欠かせません。
| 項目 | 上限内容 |
| アプリ作成数 | 最大5回まで |
| メッセージ数 | 200件まで |
| 継続利用 | 有料契約が必要 |
Difyの料金プラン

Difyは、利用目的や規模に応じて「SANDBOX」「PROFESSIONAL」「TEAM」の3種類の料金プランを選択できます。無料から導入できるため、初めてAIアプリ開発に挑戦するユーザーでも安心して試せる点が魅力です。
さらに、すべてのプランで主要なAIモデルプロバイダーに対応しており、必要に応じて段階的に利用範囲を拡大できます。
試験導入から本格的なチーム利用まで幅広く対応できる仕組みが整っている点は、大きなメリットといえます。
| プラン | 料金 | モデルプロバイダー | メッセージクレジット | 構築可能アプリ数 | メッセージリクエスト |
| SANDBOX | 無料 | OpenAI / Anthropic / Llama2 / AzureOpenAI / Hugging Face / Replicate | 200件/月 | 5 | 1日あたり5,000件 |
| PROFESSIONAL | $59/月 または $590/年 | 同上 | 5,000件/月 | 50 | 無制限 |
| TEAM | $159/月 または $1,590/年 | 同上 | 10,000件/月 | 200 | 無制限 |
試験的に利用するならSANDBOX、本格的に開発したいならPROFESSIONAL、チーム規模での利用を想定するならTEAMが最適な選択肢といえるでしょう。
Difyの利用方法
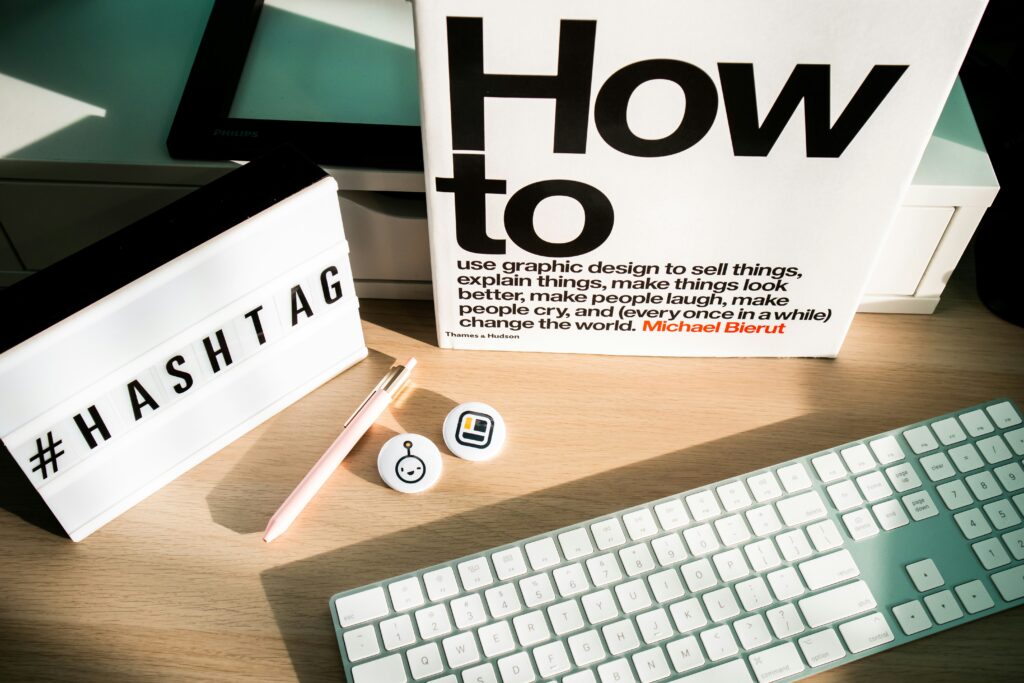
Difyを活用する際には、利用環境の選択から公開まで段階的に作業を進める必要があります。各工程を正しく実施することで、安全かつ効率的にアプリケーションを構築できるようになります。
以下の手順を参考に進めるとスムーズです。
[aside type=”boader”]AI副業6選
- 利用環境をブラウザかローカルから選択する
- 必要なワークフローを設定する
- アプリケーションの基本情報を入力する
- 外部サービスやAPI連携を行う
- プロンプトエディタを設定する
- 構築したアプリケーションをテストする
- 完成したアプリケーションを保存・公開する
関連記事:【パターン別】Difyの使い方|使いこなすコツや商用利用について
利用環境をブラウザ利用かローカル環境かで選択する
導入の第一歩は、環境選択です。手軽さを重視する場合はブラウザ、セキュリティや拡張性を求める場合はローカルが適しています。
公式サイト経由ならすぐ開始でき、Dockerを用いれば柔軟性を確保できます。
| 環境 | 特徴 | 向いているケース |
| ブラウザ | アカウント登録だけですぐ開始可能 | 手軽さ・スピード重視 |
| ローカル | Docker導入で高いカスタマイズ性と安全性 | セキュリティ重視・大規模利用 |
必要に応じたワークフローを指定する
次はワークフロー設定です。短時間で構築するならテンプレート利用、細部にこだわるなら一から作成が有効です。
AIモデルを組み込み、ニーズに合わせて流れを最適化することが重要になります。
アプリケーションの基本情報を入力する
続いて必要なのは基本情報の登録です。アプリ名や概要を明確に入力することで利用者に分かりやすい形を整えられます。適切な設定を行うと、開発後の管理や共有もスムーズになるでしょう。
外部サービスやAPIとの連携設定を行う
情報入力後は外部連携の設定が必要です。APIや外部ツールを紐づけることで機能が広がります。
適切な設定を行えば、既存システムとの統合も容易になり、業務全体の効率化が可能です。
プロンプトエディタをカスタマイズする
次はプロンプト設定です。適切なプロンプトを定義すれば回答の精度が高まります。
詳細に条件を設定すると応答の一貫性が向上し、結果として信頼性の高いアプリケーションへ発展するでしょう。
構築したアプリケーションを実際にテストする
開発が完了したらテストを行います。想定通り応答できるかを確認することが必須です。
回答が不十分な場合はプロンプトを調整し、改善を繰り返すことで完成度が高まります。
完成したアプリケーションを保存して公開する
最後のステップは保存と公開です。保存を行うことで再利用性を確保でき、作成したアプリを継続的に活用が可能です。
公開すれば他の利用者とも共有でき、社内外での展開が可能になります。
さらに、公開後に利用者から得られるフィードバックを活用することで、改善点を見つけやすくなるでしょう。
業務内容や要件が変わった場合も再編集が可能であり、継続的にアップデートを行うことで、常に実用的で高品質なアプリケーションを維持できます。
まとめ
Difyは、生成AIを専門知識なしで扱える革新的なプラットフォームであり、日本語対応や無料プラン、外部ツールとの柔軟な連携といった多くの強みを持ち合わせています。
一方で、商用ライセンスの取得が必要なケースや利用回数の制限、さらには機密情報の取り扱いに伴うリスクといった注意点も見逃せません。
導入を検討する際には、メリットとデメリットを正しく理解したうえで、自社の目的やチーム規模に合った料金プランを選択することが欠かせません。
環境の選択からアプリ公開までのステップを踏めば、効率的にAIを導入できるだけでなく、業務効率やサービス品質を大きく向上させる可能性が広がります。
今後は企業だけでなく教育や研究の分野にも活用が広がり、より多くの人がAIを日常的に取り入れる未来が期待されるでしょう。