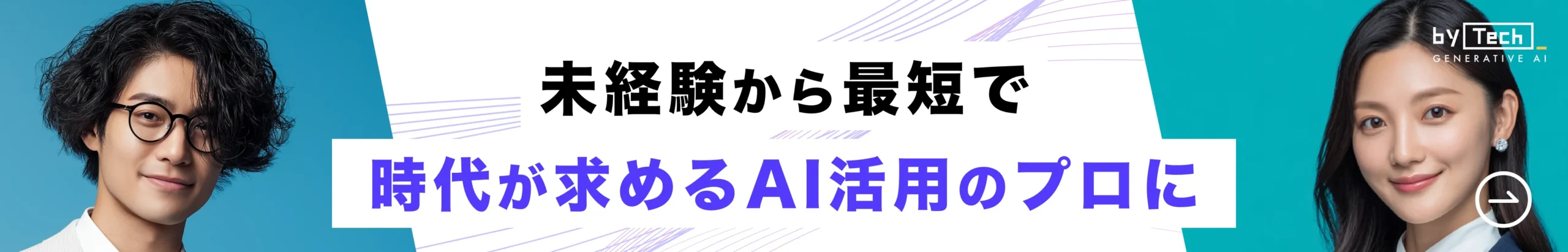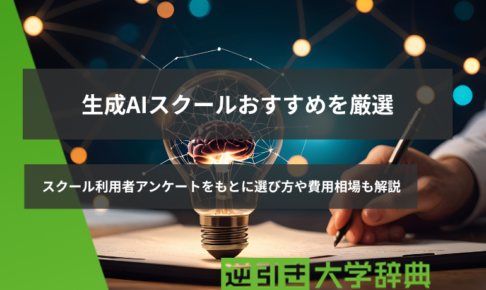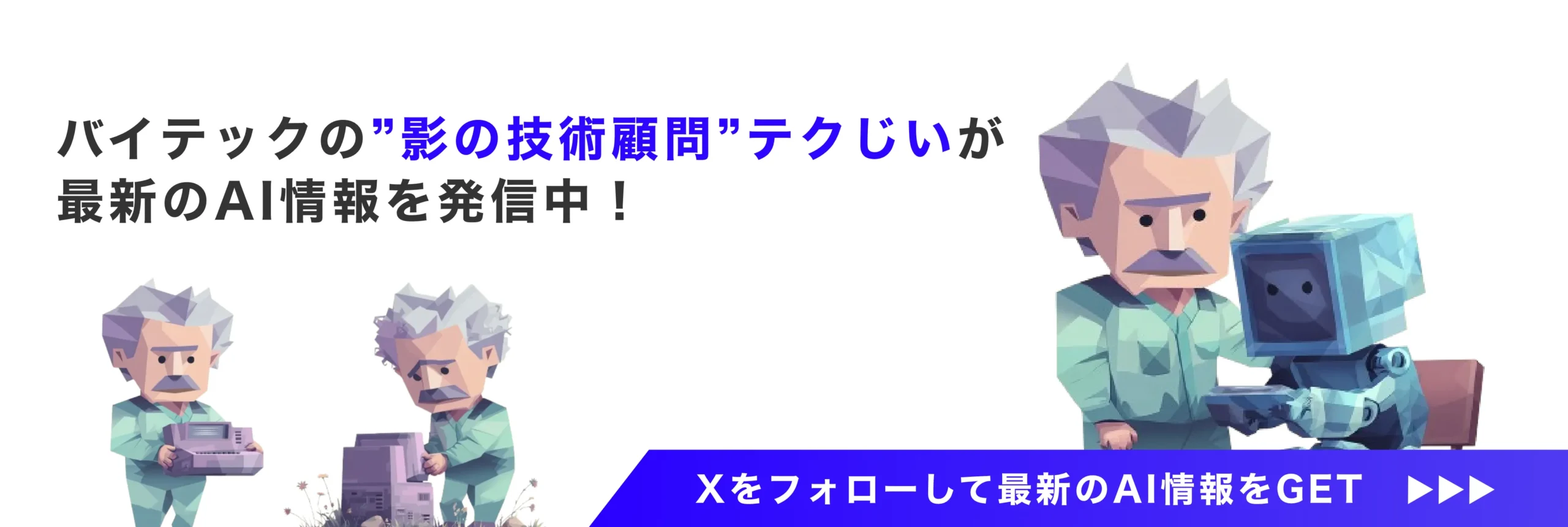Difyは、オープンソースの柔軟なAIアプリ開発基盤として注目されており、個人から企業まで幅広く活用できます。特に独自アプリケーションの開発や、社内業務効率化ツールとして導入することで、生産性向上や新たなサービス提供が可能になります。
ただし、マルチテナント環境での運用やロゴ・著作権情報の削除・変更など、一部の商用利用形態では商用ライセンスの取得が必要です。本記事では、商用利用の具体例・ライセンス取得方法・注意点を体系的に整理し、安全かつ効果的に導入するための実践ポイントを解説します。
関連記事:Difyとは|利用のメリット・デメリットや料金、使い方について
【ローカル編】Difyの基本的な使い方

Difyをローカル環境で使う際には、あらかじめDockerを準備し、GitHubからソースコードを取得してから起動・ログインする流れが必要です。各ステップごとに必要なコマンドやアクセス先が決まっているため、順序を守ることでスムーズにセットアップできます。
| ステップ | 内容 | 操作・コマンド / URL |
| 1.DockerをPCにセットアップする | PCにDockerをインストールして準備する未導入の場合は公式サイトからOS用インストーラーをダウンロードしてインストールする | Docker公式サイトからダウンロード・インストール |
| 2.GitHubからDifyを入手する | GitHubからDifyのソースコードをクローンする | git clone https://github.com/langgenius/dify.git |
| 3.Dockerを立ち上げてDifyを動かす | クローン後、Dify内のDockerディレクトリに移動しDockerを起動する | cd dify/docker docker compose up -d |
| 4.管理者アカウントを作成してログインする | コマンド実行後、ブラウザでDifyにアクセスし管理者アカウントを設定する 設定完了後はローカル環境で利用可能 | 初回設定URL:http://localhost/install 利用URL:http://localhost |
Difyのローカル版は、一度設定を完了させれば以降はブラウザから通常通り利用可能です。表の情報を参考にして、各ステップの操作内容を直感的に理解できるでしょう。
特に初めてDockerやGitHubを使う人でも、迷わず進められるように整理されています。
関連記事:DifyとGitHubの連携|重要な理由や手順、応用事例とFAQまとめ
【ブラウザ編】Difyの基本的な使い方
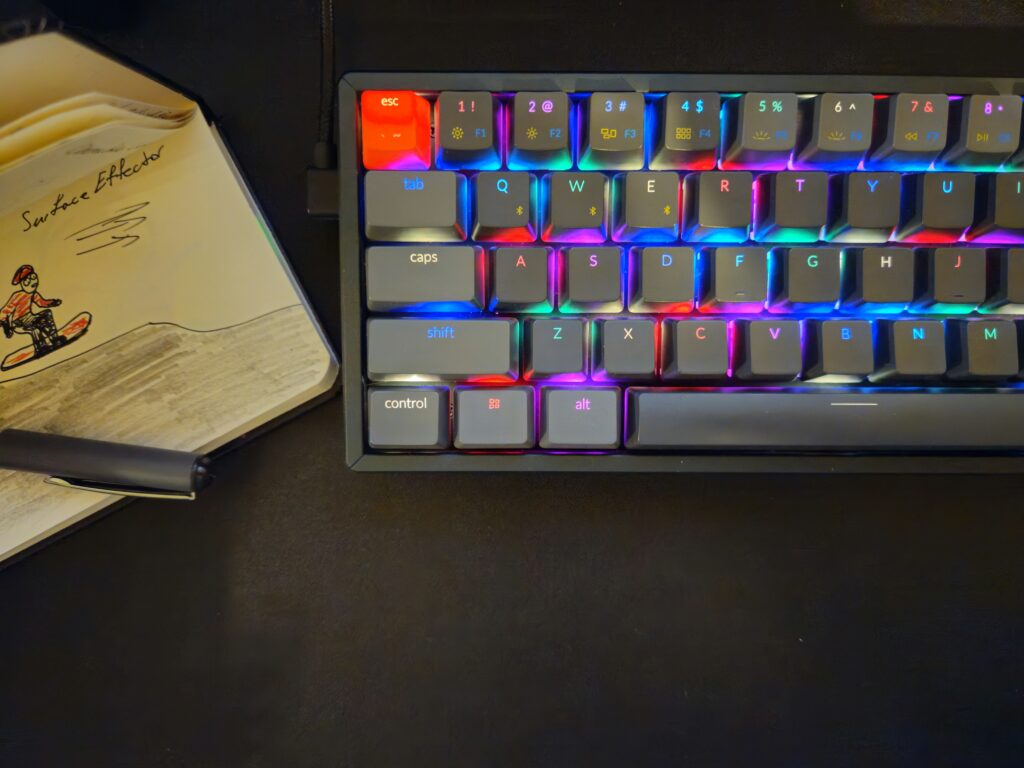
Difyをブラウザで使う場合は、公式サイトにアクセスしてログインし、ワークフロー選択・基本情報入力・LLMの設定・プロンプトの作成・テスト・公開という順に進めます。インストール不要で、クラウド上ですぐにアプリ構築が始められるのが特徴です。
| ステップ | 内容 | 操作ポイント |
| 1.Difyの公式ページを開いてログインする | 公式サイトにアクセスしてGitHubまたはGoogleアカウントでログインするアカウントがない場合は事前に作成する必要あり | 公式サイトでログイン |
| 2.ワークフローを選び、アプリの基本情報を入力する | 「最初から作成」または「テンプレートから作成」を選び、アプリ名・概要・アイコンなど基本情報を入力して「作成する」をクリック | 作成モードを選択し、基本情報を設定 |
| 3.利用したいAIモデル(LLM)を選択する | 使用するLLMのAPIを選択し、必要に応じてOpenAIやGoogle CloudなどのAPIキーを追加設定する | 設定画面からAPIを選択・追加 |
| 4.プロンプトを設定してAIの動作を調整する | 「手順」欄にプロンプトを入力し、AIモデルの応答方法を細かく設定する | 高品質なプロンプトで精度向上 |
| 5.アプリをテストし、動作を確認して公開する | 「デバッグとプレビュー」で開発したアプリをテストし、問題なければ保存・公開する公開後も編集・更新が可能 | テスト→保存・公開 |
Difyのブラウザ版は、クラウド上で簡単にAIアプリを構築できる点が魅力です。表を参考にすることで、どの段階で何を設定すべきか、作成したアプリをどのように公開・更新するかが明確になります。
Difyを使いこなすためのポイント4選
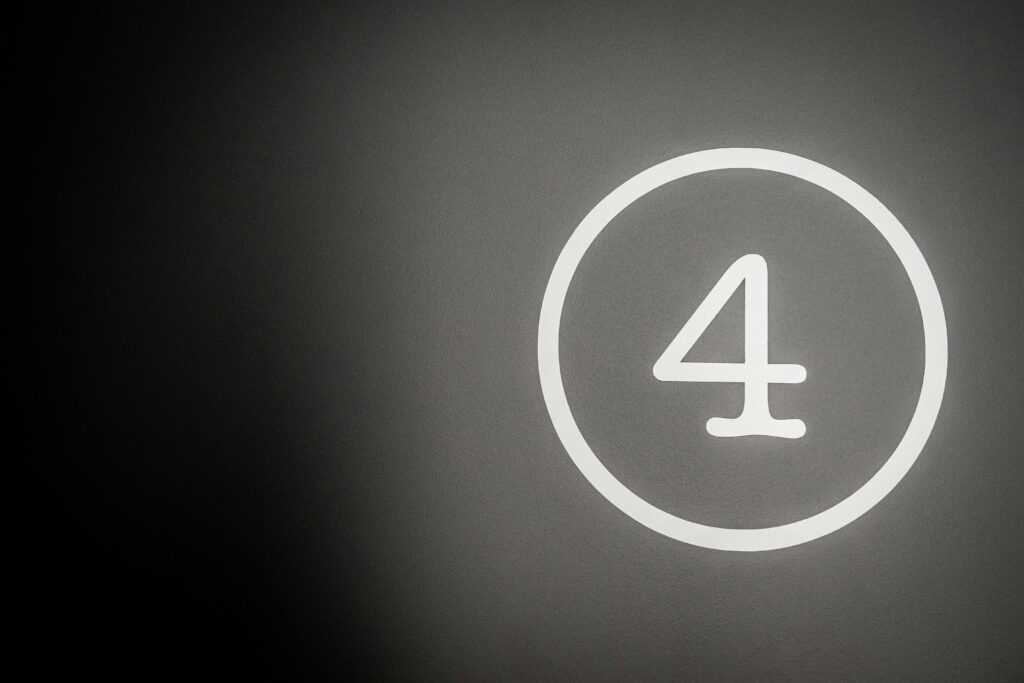
Difyを業務に導入する際は、単にツールを利用するだけでは本来の価値を十分に発揮できません。長期的な成果を得るためには、情報管理や教育体制・プロンプト設計・メンテナンスなど複数の観点から環境を整えることが大切です。
以下に挙げる4つの視点を押さえることで、安定した運用や高い成果を維持できる仕組みが整います。企業の規模や用途に合わせて実践しやすいポイントを選び、AIアプリ開発の質とスピードの両立が可能になります。
セキュリティと機密情報管理の徹底
AIアプリを安全に活用するためには、堅牢な情報管理体制を構築することが不可欠です。顧客情報や社内データを扱う場合、外部サービスへの預託リスクを抑えるためにオンプレミス環境にDifyを導入する方法が有効です。
また、利用するAIモデルによってはデータが外部に送信される可能性があるため、アクセス権や利用範囲を明確に設定していただく必要があります。さらに、機能を区分し運用ガイドラインを整備することで、社内の混乱や誤用を防げます。
| リスク要因 | 推奨対策 |
| 外部モデルへのデータ送信 | 送信対象データの制限やAPI利用ポリシーの策定 |
| 社内混乱・誤用 | 機能区分・運用ガイドラインの策定と周知 |
AIリテラシーと教育体制の確立
ノーコードでAIアプリ開発が可能であっても、基本概念を理解していなければ成果が限定的になるでしょう。社内に導入する際には、利用目的や適用範囲を明文化し、ユーザー向けに研修や操作マニュアルを整備することが欠かせません。
また、社内ポータルで事例を共有したりFAQを整備したりすることにより、使い方が浸透しやすくなります。AI活用を試行にとどめず、組織文化として定着させる継続的な学習支援が、DX推進の重要な要素となります。
<教育体制で整備すべきもの>
- 研修・勉強会の実施
- 操作マニュアルの整備
- 社内ポータルで事例共有
- FAQページの作成
プロンプト設計とワークフロー機能の活用
Difyの機能を最大限活かすためには、単なるチャット機能にとどめず、複数プロセスを組み合わせたワークフロー設計を行うことが有効です。問い合わせの要約やデータ検索、結果生成といった処理を分割して設計していただくことで、出力の精度が高まります。
さらにRAGエンジンを活用すると、社内データベースと連携した高精度な応答が実現できます。FAQ対応や、文書検索など幅広い用途に応じた自然言語処理が可能になり、業務効率化を推進できるでしょう。
| 活用場面 | 期待できる効果 |
| 問い合わせ要約 | 迅速な対応 |
| 社内情報検索 | 精度の高い回答 |
| 応答結果生成 | 作業負荷の軽減 |
アプリケーションの定期的なメンテナンスと拡張
AI技術は日々進化しているため、Difyで構築したアプリケーションも継続的なメンテナンスが不可欠です。定期的なバージョンアップやバックアップ、不要データの整理などを怠ると、処理速度や出力品質が低下するリスクがあります。
また、SlackやGoogle検索など、外部ツールとの連携を段階的に広げる計画を持っていただくことで柔軟に機能の拡張が可能です。運用管理と拡張戦略を同時に進めることが、長期的な業務改革を実現する鍵となります。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
| 定期的に実施すべき管理項目 | システムの安定稼働を維持するために、定期的に点検・更新を行う内容 | バージョンアップやパッチの適用バックアップおよびリストアテストアクセス権限の見直し・不要データの整理と削除 |
| 拡張計画に含めると良いこと | 将来的な利便性や、機能拡張を見据えて計画的に取り入れるべき項目 | 外部ツールやAPI連携機能の段階的追加自社業務フローに合わせた機能カスタマイズ |
Difyの商用利用について

Difyは、Apache License 2.0をベースに公開されているオープンソースプロジェクトです。一定の条件を満たせば、企業や個人が開発したアプリケーションやサービスに組み込み、商用利用することが可能です。
具体的には、独自アプリケーションの販売・サブスクリプション形式の提供・社内業務効率化ツールとしての導入など、多彩な形での活用が認められています。ただし、マルチテナント環境での利用やロゴ・著作権情報の削除など、制限に該当する場合は商用ライセンス取得が必要となります。
Difyの商用利用が可能なケース
Difyは、独自開発したAIアシスタントや業務支援ツールなど多様な形態で商用利用が可能です。以下の表に、代表的な利用ケースを整理しました。
| 利用ケース | 内容概要 |
| 独立環境構築・カスタマイズ | クライアントごとに特化したAIアシスタントを開発し、その環境をホスティングするサービスの提供 |
| 独立型アプリの有料販売(買い切り) | 特定業務を自動化するAIツールやエキスパートシステムを開発し、有料販売やAPIキー販売を行う |
| API活用アプリのサブスク販売 | LLMモデルを組み込んだ高度な自然言語処理アプリなどをサブスクリプション形式で提供 |
| セールス・マーケティング利用 | 顧客対応チャットボットを開発し、製品案内やアフィリエイト誘導を行う |
| 社内業務効率化ツール | ナレッジベース連携やマニュアル自動生成など、社内向けツールを開発・導入する |
Difyの商用利用はライセンスが必要なこともある
Difyの一部の商用利用形態では、商用ライセンスの取得が求められます。特に注意すべき条件を以下にまとめました。
- マルチテナントサービスでの運用
- Difyのロゴおよび著作権情報の削除・変更
| 区分 | 内容 | 対応方針 |
| マルチテナントサービスの取扱い | 書面による許可がない場合、マルチテナント環境での運用は不可複数ワークスペース構成は商用ライセンスの対象 | マルチテナントで利用する際は、事前に商用ライセンスを取得する。単一ワークスペースでの運用を推奨。 |
| ロゴおよび著作権情報の削除・変更 | ロゴや著作権情報の削除・変更は禁止フロントエンドで改変する場合は商用ライセンスが必要 | ロゴや著作権情報はそのまま保持する。改変する場合は商用ライセンスを取得する。 |
Difyの商用利用におけるライセンス取得について
商用ライセンスが必要な場合は、TDSEへ問い合わせて手続きを行います。
以下の表は、基本的な流れを整理したものです。
| ステップ | 内容 |
| 問い合わせと条件確認 | 商用ライセンスが必要か判断できない場合もTDSEへ連絡し、目的や構成を説明したうえで必要性を確認する |
| ヒアリングと案内 | 利用目的・規模・構成に基づき、必要なライセンス形態や料金目安について案内を受ける |
| ライセンス契約の締結 | 条件に合意後、正式に契約を締結する特にマルチテナント利用の場合は契約書に明記されていることを確認する |
| サポート体制 | TDSEは商用利用を円滑に進めるため、丁寧なサポートを提供する疑問点がある場合は早めに相談することが重要 |
Difyにおける商用利用の注意事項
Difyの商用利用を進めるにあたり、以下の3点に注意することが求められます。
| 注意点 | 内容 |
| オープンソースライセンスの理解 | Apache License 2.0を基に公開されており、商用ライセンスが必要になる場合があるため内容を確認する英文が理解できない場合はTDSEへ相談する |
| 商用ライセンスを取得しない場合の表示義務 | 商用ライセンスを取得しない場合はDifyのロゴと著作権情報を正確かつ視認しやすい位置に明記する外観や内容を変更しない |
| ガイドライン・マニュアルの策定 | 従業員全員へライセンスに基づいたガイドラインやマニュアルを配布する必要に応じて研修・教育を実施して違反防止を図る |
まとめ
Difyは、Apache License 2.0を基に公開されており、多様な形態での商用利用が可能です。独立環境構築やアプリ販売・サブスク提供・マーケティング利用・社内業務効率化ツールなど、幅広い活用シーンが存在します。
一方で、マルチテナントサービスでの利用やロゴ・著作権情報の削除・変更など、特定の条件では商用ライセンスの取得が求められます。導入前にオープンソースライセンスの内容を確認し、表示義務や社内ガイドラインを整備することが重要です。
適切な手続きを踏むことで、Difyを安全かつ効果的に活用できます。