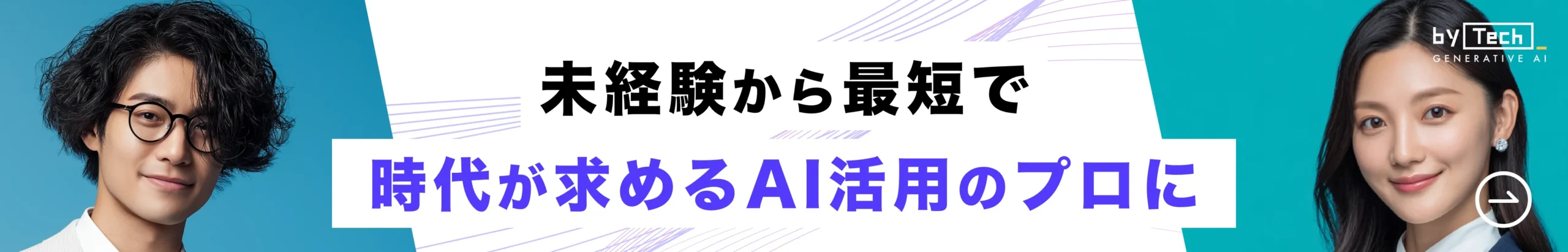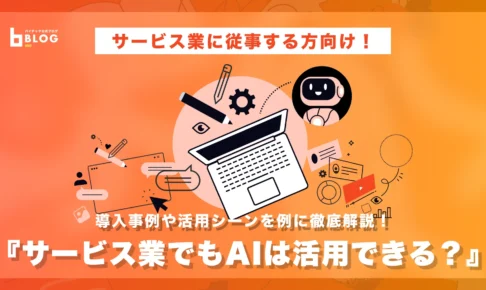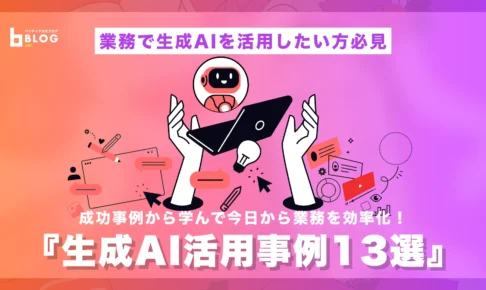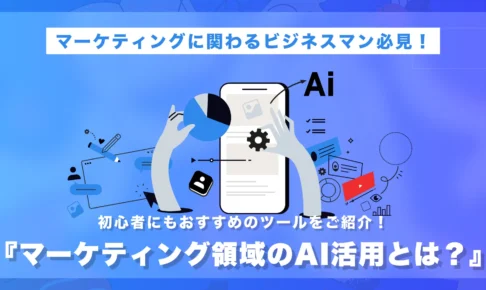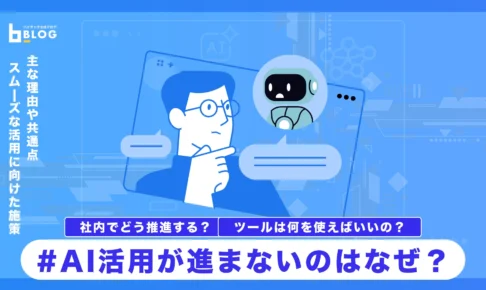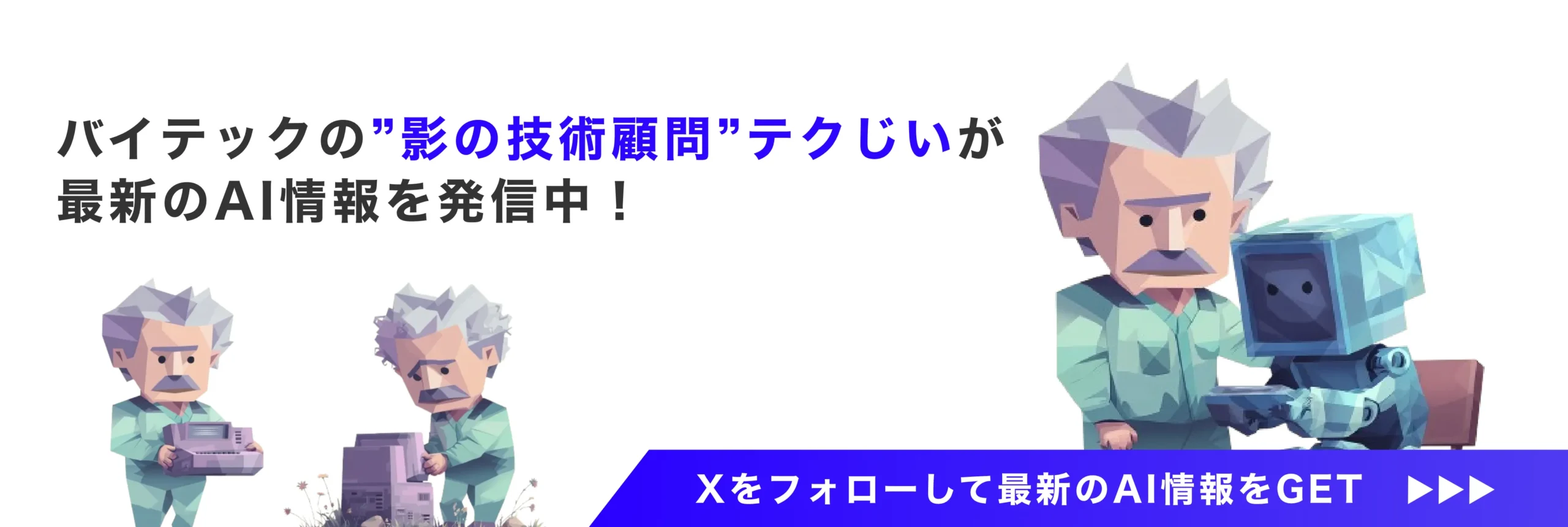生成AIの活用が進む現在、RAG(検索拡張生成)はAIの回答精度と信頼性を高めるために欠かせない技術となっています。Difyを用いたRAG構築では、専門的なプログラミング知識を必要とせず、自社のナレッジを反映した高品質なAIチャットボットの実装が可能です。
RAGの設計や運用においては、データ構造の最適化・プロンプト設計・セキュリティ体制の整備など、多角的な工夫が成果を左右する要因とされています。本記事は、Difyを活用したRAG構築の全体像と、実務で成果を高めるための設計・運用の要点を丁寧に解説する内容です。
生成AIに興味はあるけど、どうやって勉強すればいいんだろう…』
そんな方へ、
- AI副業で収益化するためのテクニック
- ChatGPTなどの生成AIを業務で活用するためのコツ
- 生成AIの効率的なキャッチアップのコツ
を、無料のオンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします!
さらに参加者限定で「AI副業ロードマップ」「ChatGPT完全攻略ガイド」など、豪華10点をプレゼント!🎁
パソコンはもちろん、スマホから気軽に参加OK。この1時間が、あなたを変える大きなきっかけになりますよ。
\ スマホから参加OK /
RAG(検索拡張生成)とは
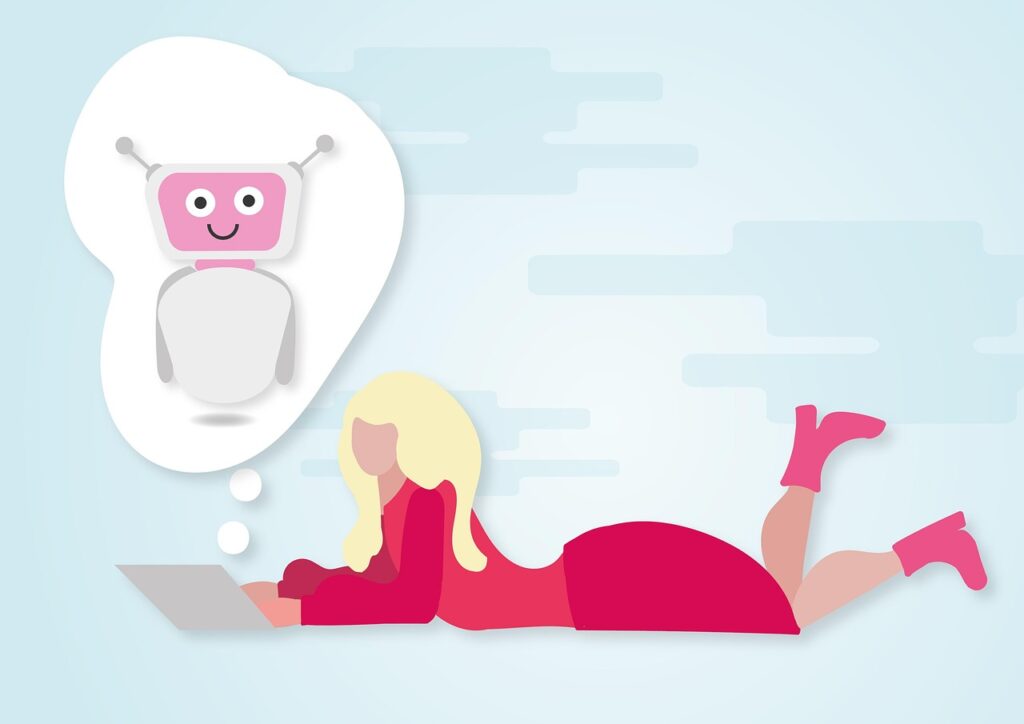
AIが生成する文章は便利ですが、事実と異なる内容を出力するリスクや、最新情報を反映できない課題が存在します。RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、こうした課題を克服する仕組みとして注目を集めています。
RAGは、大規模言語モデルが外部データベースを参照し、信頼できる情報を根拠に回答を組み立てるフレームワークです。RAGは、業務利用に求められる正確性と更新性の両立を実現します。以下では、RAGの仕組みや特長を詳しく解説します。
RAGが解決するハルシネーションや情報鮮度の課題
RAGは、言語モデルが事実と異なる回答を生成する「ハルシネーション」の発生を防ぐために開発されました。通常のモデルは学習データに依存するため、古い情報や内部資料などを反映できません。
RAGを導入すると、AIは質問内容に関連するデータを外部ナレッジベースから検索し、検索した情報を根拠に回答を作成します。生成結果が常に最新で、かつ裏付けのある内容となります。
特に社内マニュアルや顧客データを扱う分野では、信頼性を大幅に高められる点が大きな利点です。
<RAG導入による主な効果>
| 課題項目 | RAGによる改善内容 |
| ハルシネーション | 参照データを根拠に事実性を確保 |
| 情報の古さ | 外部データベースから最新知識を取得 |
| 独自データの反映 | クローズド環境の知識も回答に反映可能 |
検索と生成の2段階で処理される情報フローの仕組み
RAGの動作は「検索」と「生成」の2つの工程で構成されます。最初に質問内容を数値ベクトルに変換を行い、ナレッジベースに保存されたデータと意味的に比較し、関連度の高い情報を抽出のうえ、AIが参照できる文脈として渡します。
次に、言語モデルがその情報を基に自然な文章を組み立て、人間にとって理解しやすい回答を生成します。以下に、各工程の役割を整理しました。
| 処理段階 | 内容 | 主な役割 |
| 検索(Retrieval) | 質問をベクトル化し、ナレッジベース内の情報と意味的に照合 | 関連する事実情報を抽出する |
| 生成(Generation) | 抽出された情報(コンテキスト)を基に自然な文章を生成 | 文脈を踏まえた正確で自然な回答を作成する |
上記の仕組みにより、単なるキーワード検索よりも文脈を理解した応答が可能となり、FAQやカスタマーサポートの自動化に大きな効果を発揮します。
LLMの再学習が不要なファインチューニングとの違い
RAGの特徴は、モデルそのものを再学習させる必要がない点にあります。ファインチューニングでは、新しいタスクに合わせてモデル内部のパラメータを調整するため、高度な知識と時間が不可欠です。
一方、RAGは外部データベースを参照し、必要な情報を検索して取り込むだけで最新データを反映できます。運用負荷を抑えつつ柔軟に運用できる点が強みです。
| 項目 | RAG | ファインチューニング |
| 学習方法 | 外部データを参照して動的に応答生成 | モデル内部パラメータを再学習 |
| 更新の容易さ | データベース更新のみで反映可能 | モデル再学習が必要 |
| 導入コスト | 低い(構築が比較的簡単) | 高い(専門知識と時間が必要) |
| 適した用途 | 最新情報や機密データを扱う業務 | 特定タスクの精度を高めたい場面 |
特に複数のモデルを併用する場合、RAGは再学習を行わずに各モデルの特性を活かせます。加えて、社内データや非公開情報を安全に統合できるため、精度とセキュリティを両立できるのが大きな利点です。
RAG×Difyで実現する4つのメリット

RAGの導入は、専門知識がなくても業務効率化を実現できる手段として注目されています。中でもDifyを活用することで、AIアプリ開発がより柔軟かつ安全に行えるようになります。
Difyは、オープンソースとして提供され、直感的な操作でナレッジベースを構築でき、複数のモデルや外部ツールとも連携可能です。加えて、オンプレミス運用にも対応しており、セキュリティを重視する組織にも適しています。
以下では、DifyとRAGを組み合わせることで得られる4つの具体的な利点を紹介しましょう。
初心者でも直感的にAIアプリを構築できる
Difyは、ノーコードやローコードでAIアプリケーションを開発できるプラットフォームです。画面上でのドラッグ操作だけで、チャットボットやエージェントを簡単に作成できます。
複雑なプログラミングが不要なため、専門部署に依頼せずとも現場担当者が自らアプリを改善できます。さらに、AIの発言トーンや回答範囲を柔軟に設定でき、業務の変化に合わせた迅速な調整が可能です。
<直感的に構築できる理由>
| 要素 | 特徴 |
| UI設計 | ドラッグ&ドロップで構築可能 |
| 開発スキル | コーディング不要 |
| 更新作業 | 非エンジニアでも設定変更が容易 |
操作性に優れた設計により、IT知識の差を問わずAI導入をスムーズに進められます。
多様なデータソースを一元管理できる
Difyのナレッジベース機能を利用すれば、複数形式のデータを一元管理できます。PDF・Excel・HTML・JSONなどの異なる形式のファイルを取り込み、AIの回答精度を高められるでしょう。
さらに、NotionやWebサイトなどオンライン情報も自動で統合可能です。社内文書やマニュアルを即座に活用でき、情報共有のスピードが向上します。
- PDF・Word・CSVなどの社内資料を即時登録
- WebページやNotion情報を自動で取得
- 構造化・非構造化データの両方を活用
業務データを分散管理する必要がなくなり、情報活用の一貫性を確保できます。
オンプレミス/セルフホスト運用が可能になる
Difyは、オープンソースのためクラウドだけでなく社内サーバー上にも導入が可能で、自社ネットワーク内でAIを運用できる点が大きな特徴です。社外通信を遮断しても動作するため、機密情報を扱う企業でも安心して利用できます。
また、ソースコードを改変し、自社独自の拡張機能を追加することも可能です。
| 運用形態 | 特徴 | メリット |
| クラウド環境 | 迅速な導入が可能 | 開発コストを削減 |
| オンプレミス環境 | 自社サーバー上で稼働 | 情報漏えいリスクを低減 |
セキュリティ要件を満たしつつ、AI活用の自由度を高められる仕組みです。
複数のLLMや外部ツールとのAPI連携による高い拡張性がある
Difyは、ChatGPTやClaude・Llamaなど、複数のLLMを切り替えて利用できます。業務内容に応じて最適なモデルを選択できるため、柔軟なAI構築が可能です。
さらに、Google検索やSlack・Notionなどの外部ツールとも連携でき、業務システムとシームレスに統合できます。
- 業務ツール間の情報連携を自動化
- 外部検索を組み合わせた高精度回答
- 複雑なワークフローをAIが自動処理
Difyの拡張性によって、AIの適用範囲を広げ、組織全体の生産性を向上させることが可能です。
【6ステップ】DifyでRAGチャットボットを構築する流れ
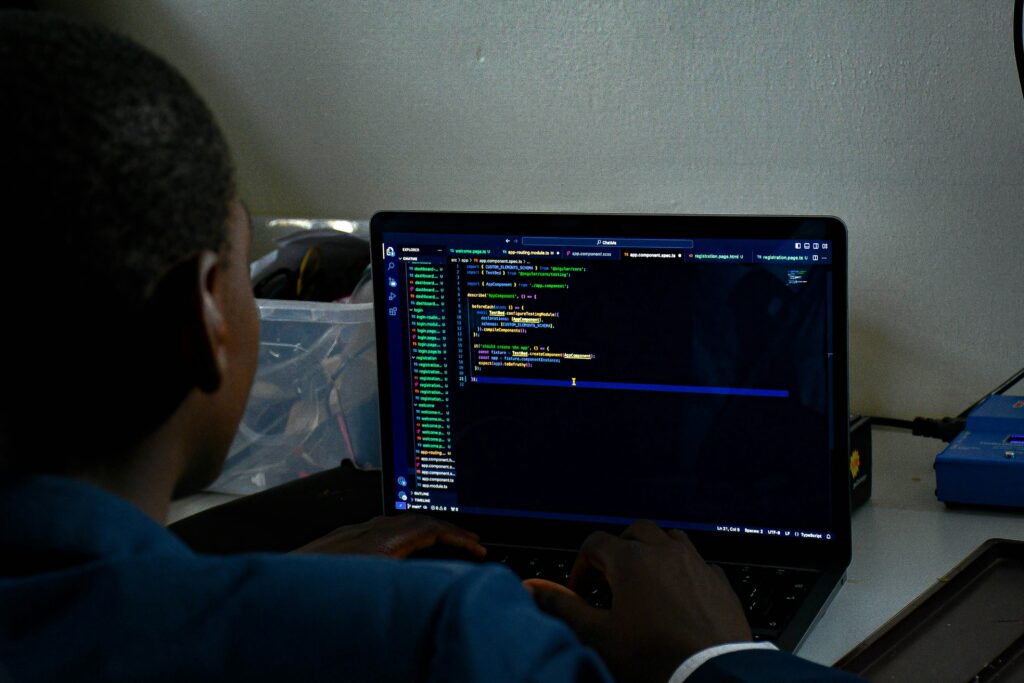
RAGを活用したチャットボットは、企業や個人が独自の知識を活かしてAIを運用するための重要な仕組みです。Difyを使えば、専門的なコーディングを行わずに高品質なRAGチャットボットを短時間で構築できます。
手順を段階的に進めることで、初心者でも運用レベルのシステムを完成させることが可能です。以下では、構築から公開までの6つの手順をわかりやすく説明します。
1.Difyアカウントのセットアップ
まず、Dify公式サイトでアカウントを登録します。「始める」ボタンから案内に沿って進むと、GoogleまたはGitHubで簡単にサインインが可能です。
登録後は、利用したいLLMのAPIキーを「設定」メニューから入力しましょう。OpenAIやCohereのキーを追加すれば、Dify上で直接利用できます。
無料のSANDBOXプランでもRAG機能を試せますが、利用クレジットの上限を確認しておくと安心です。
<セットアップ手順まとめ>
| 手順 | 操作内容 | 備考 |
| ① | アカウント登録 | Google / GitHub連携可 |
| ② | APIキー登録 | OpenAIやCohere対応 |
| ③ | 動作確認 | 無料プランで検証可能 |
2.参照させたいドキュメントをナレッジベースに登録
RAGの中核を担うのが、参照情報の登録です。上部メニューの「ナレッジ」から新しいベースを作成し、PDFやTXT、Wordなどの文書をアップロードします。
登録後は、「チャンク設定」や「検索モード」を調整し、目的に合った精度で検索できるようにします。ハイブリッド検索を選択すれば、全文一致と意味検索の両方の活用が可能です。
- PDFやTXTファイルをアップロード
- チャンクサイズと検索モードを設定
- 「保存して処理」で登録完了
データの質と検索方法を最適化することで、AIの回答精度が大幅に向上します。
3.スタジオからチャットボットアプリケーションを作成
ナレッジの準備が整ったら、アプリケーションの作成に進みます。上部ナビゲーションの「スタジオ」から「最初から作成」を選び、「チャットボット」を指定しましょう。
アプリ名やアイコンを入力し、「作成する」をクリックすると編集画面に移動します。初期状態では、「開始」「LLM」「回答」の3ノードが自動で接続された状態になっています。
これらのノードを活用することで、対話の流れや出力内容を自由な設計が可能です。用途に応じてノードを追加すれば、より高度なチャット体験を実現できるでしょう。
4.作成したナレッジをコンテキストとして連携設定
作成したアプリに、登録済みのナレッジベースを連携させます。設定画面で「コンテキスト」欄の「+追加」をクリックし、登録済みの知識を選択します。
選択後に「追加」を押すと、AIは質問を受けた際、ナレッジ情報を参照して回答を生成するようになるでしょう。
<連携設定の手順>
- 設定画面で「コンテキスト」を開く
- 「+追加」をクリックしてナレッジを選択
- 「追加」を押して反映
- 保存後に動作を確認
RAGの連携により、一般知識ではなく自社固有情報を基にした応答が可能です。業務マニュアルや製品情報を組み込めば、現場対応力を高めるAIの構築ができます。
5.参照元を明示する「引用と帰属」機能を有効化
AIの回答に信頼性を持たせるためには、情報の出典を明示することが重要です。「引用と帰属」機能を有効化すると、AIが参照したドキュメントの名称やリンクを自動表示できます。設定画面の「有効な機能」から「引用と帰属」をオンにするだけで適用されます。
<引用機能を使うメリット>
- 回答の根拠が明確になり信頼性が高まる
- 利用者が参照元を確認できる
- 社内利用でも情報追跡が容易になる
透明性の高いAI応答を実現し、企業内外での信頼を確立できる点が大きな魅力です。
6.動作確認とアプリケーションの公開
最後に、設定内容を確認します。右側の「デバッグとプレビュー」で質問を入力し、登録したナレッジを参照して回答しているかをテストします。
引用元が正しく表示され、内容が正確であれば設定は完了です。「公開する」ボタンからアプリを公開し、発行されたURLを共有すれば他のユーザーも利用できます。
<チェックリスト>
| 確認項目 | 内容 | 判定基準 |
| 回答内容 | 登録ナレッジを反映しているか | 参照内容が一致している |
| 引用表示 | 出典が明示されているか | 正しいリンクが付与されている |
| 公開設定 | URL共有が有効か | 他ユーザーがアクセス可能 |
動作確認を丁寧に行うことで、運用後のトラブルを防ぎ、安定したAI応答を維持できるでしょう。
回答精度を劇的に高めるRAGの高度な設計手法
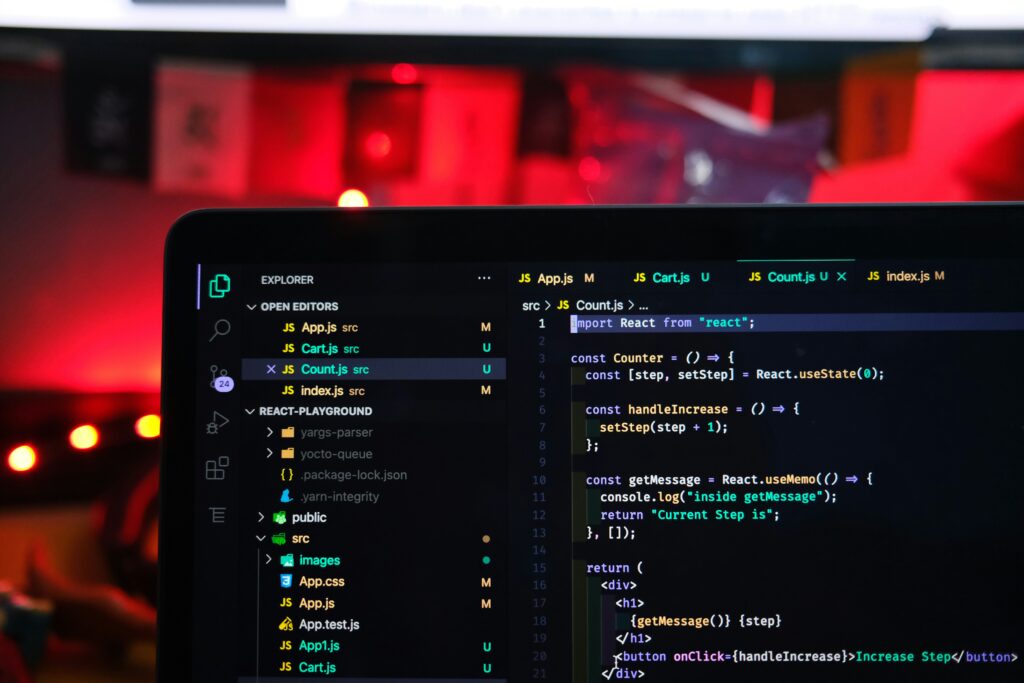
RAGは高精度な情報検索を実現しますが、質問内容が曖昧だったり、文脈が複雑な場合には誤った回答を導くことがあります。質問の曖昧さや文脈の複雑さを補う手段として注目されているのが、RAGを補強する三つの高度設計手法です。
HyDE・Self-Route・GraphRAGを導入することで検索段階や判断工程を最適化し、情報の正確性と一貫性を飛躍的に高められます。以下では、各特徴とDifyでの活用方法を解説しましょう。
HyDE
HyDE(Hypothetical Document Embeddings)は、質問が漠然としている場合に検索精度を高める手法です。まずLLMが質問に対して仮説的な回答文を生成し、生成した文を検索クエリとして利用します。
理想的な回答の文脈でナレッジベースを探索するため、より意味的に関連した情報を取得できます。
<HyDEの仕組み>
| 工程 | 内容 | 目的 |
| 仮説文生成 | LLMが一時的に理想回答を作成 | 曖昧な質問を具体化 |
| 検索処理 | 生成文をクエリとして検索 | 意味的に近い情報を抽出 |
| 結果生成 | 抽出データを基に回答作成 | 精度の高い応答を生成 |
Difyでは、Chatflow上のLLMノードで仮説文を生成し、検索ブロックに変数として渡すことでHyDEの再現が可能です。
Self-Route
Self-Routeは、RAG情報を使うかどうかをAI自身に判断させる仕組みです。質問内容によっては、ナレッジを参照せずに回答した方が正確な場合があります。
Self-Routeでは、LLMが「RAG情報を利用」「RAG情報を省略」「全文を活用」の三つの処理ルートを選択します。
- RAG情報を使わない方が正確なケース
- ナレッジ全体を要約に活かすケース
- 一部情報のみを抽出して回答するケース
Difyでは、「ルート判断」ブロックと「IF/ELSE」構造を組み合わせ、質問ごとに処理経路を分岐させて無関係な情報の影響を排除し、回答の整合性の維持が可能です。
GraphRAG
GraphRAGは、情報同士の関係性をネットワーク構造として扱い、知識を「ノード」と「エッジ」で表現する技術です。単なる意味類似検索ではなく、情報間の結びつきを考慮するため、複雑なテーマや多段階の推論にも対応できます。
| 項目 | 内容 |
| データ構造 | ノード(概念)とエッジ(関係)をグラフで表現 |
| 強み | 文脈理解・関係推論が可能 |
| 利用方法 | 外部GraphRAGエンジンをAPI化し、DifyのChatflowに連携 |
| 留意点 | 高精度だが計算負荷と管理コストが大きい |
上記構造化検索によって、単純なキーワード一致では得られない精密な情報抽出が可能となりました。
RAG精度を左右するナレッジデータ作成のコツ

RAGの性能を安定して引き出すためには、学習データや検索対象となるナレッジの設計が重要です。チャンク化の粒度や検索設定の選定、さらに非構造化データの整備は、回答の正確性と再現性を大きく左右します。
特にDifyでは、ナレッジ登録時に細かな設定を調整できるため、設計段階の工夫がそのまま成果物の品質に直結します。以下では、精度を最大限に高めるための3つの設計ポイントを解説しましょう。
チャンク化とオーバーラップの設計
チャンク設計は、RAGの回答品質を支える基礎要素です。データをLLMが処理しやすい単位に分割する際、チャンクの長さが長すぎると文脈が飛び、短すぎると必要情報が欠落します。
一般的には500〜512トークン程度が目安とされます。また、隣接するチャンク間に100〜128トークン程度の重複を設けると、文脈を保ちながら精度の向上が可能です。
<チャンク設計のポイント>
| 項目 | 推奨値 | 効果 |
| チャンク長 | 約500〜512トークン | 文脈の断絶を防止 |
| オーバーラップ量 | 約100〜128トークン | 前後関係を維持 |
| 設定方法 | Difyのナレッジ編集画面 | 区切りプレビューで確認可能 |
チャンクと重複を適切に設計することで、検索段階の情報欠損を防ぎ、安定した回答を得られます。
ハイブリッド検索の設定
検索モードの選定は、RAGの性能を最大化するうえで重要な要素です。Difyでは「ベクトル検索」「全文検索」「ハイブリッド検索」の三つから選択でき、目的に応じて最適な方式を組み合わせることができます。
ベクトル検索は意味的関連性の理解に優れ、全文検索は固有名詞や専門語の照合に強みがあります。両者の特徴を併せ持つハイブリッド検索は、幅広い質問に対して精度の高い応答を実現できる仕組みです。
<検索方式の比較表>
| 検索方式 | 特徴 | 強み |
| ベクトル検索 | 意味的な関連性を重視して照合する仕組み | 抽象的な質問や多言語検索に強い |
| 全文検索 | テキスト内の完全一致を基準に検索を行う方式 | 固有名詞や専門用語の正確な一致に優れる |
| ハイブリッド検索 | 意味検索とキーワード検索を統合した方式 | 精度と再現性のバランスを両立できる |
業務マニュアルやFAQのように、意味理解と語句一致の両方が求められる分野では、ハイブリッド検索を採用することで正確性と網羅性を同時に確保できる構成となります。
非構造化データを事前に構造化する重要性
ナレッジとして扱うデータ形式によって、RAGの回答精度は大きく変化します。PDFやWordのように段落構造が不明確な文書を直接使用すると、内容の一部が正しく抽出されないことがあるでしょう。
XMLやJSONのような構造化データに変換して登録すれば、情報の階層や関連性が明確化され、回答の一貫性が向上します。
<文書整形による主な利点>
- 検索時のセグメント誤認を防止
- 情報抽出の精度を向上
- 回答の再現性と安定性を確保
構造化の手間は発生しますが、RAGの品質を長期的に保つ上で最も効果的な対策といえるでしょう。
Dify RAGの導入事例と成功のポイント5選

RAGを業務に活かすためには、単にAIを導入するだけでなく、運用目的や管理体制を明確に設計する必要があります。特にDifyを用いたRAG構築では、目的設定からセキュリティ対策、精度向上までを体系的に進めることが重要です。
導入効果を最大化するためには、初期設計から運用までの一貫した体制が欠かせません。以下では実際の導入事例を踏まえ、成果を出すための5つの成功要素を紹介します。
導入目的と達成したい具体的な目標の設定
AG導入の第一歩は、明確な目的設定です。AI活用の方向性を定めずに進めると、投資効果が曖昧になります。
FAQ自動化や社内検索精度の改善など、解決したい課題を具体化し、達成したい数値目標を設定することが重要です。
<目的設定の例>
| 項目 | 内容 | 目標例 |
| 活用領域 | FAQ自動応答 | 問い合わせ対応80%削減 |
| 業務効率化 | 社内検索最適化 | 検索時間50%短縮 |
| 品質管理 | 回答精度の改善 | 正答率90%達成 |
目標を明確化することで、AI導入が単なる試験的取り組みではなく、業務改善施策として成果につながります。
現場担当者によるナレッジの柔軟な更新体制の構築
RAGの性能を維持するには、常に最新情報を反映できる更新体制が求められます。Difyはノーコード基盤を採用しており、専門的知識を持たない担当者でも操作可能です。
業務部門が直接ナレッジを追加・編集できるため、IT部門を介さずに即時反映が行えます。
- ドキュメントをドラッグ&ドロップで追加
- 既存データを上書きして即時更新
- 現場主導でナレッジ品質を維持
現場が自走できる環境を整えることで、AIが常に正確な情報を返し、運用コストの削減も可能です。
ハルシネーションを抑制するプロンプトと回答ルールの設定
回答精度を高めるためには、LLMへの指示設計が不可欠です。プロンプト内で役割や制約を明示することで、回答の一貫性を確保できます。
具体的には、回答時の情報源を指定したり、情報が存在しない場合の応答ルールを設定する方法が有効です。
<信頼性を高める設定例>
- 「必ず指定されたコンテキストを使用して回答する」
- 「出典元や規定番号を明記する」
- 「情報がない場合は『該当情報なし』と回答する」
明確なルールを設けることで、誤情報の生成を防ぎ、企業利用にも耐えうる信頼性を確保できます。
機密情報保護のためのセルフホスト運用
社内データを扱うRAGでは、情報漏れの対策が必須です。Difyはオンプレミス(セルフホスト)環境に対応しており、自社サーバー上で運用し、クラウド依存を避けつつ高いセキュリティを維持できます。
| 項目 | 内容 | メリット |
| 運用環境 | 自社サーバー運用 | 機密情報を外部に送信しない |
| 権限管理 | アクセス制限設定 | 閲覧範囲を明確化 |
| セキュリティ | 通信遮断運用 | 情報流出リスクを軽減 |
独自データを安全に取り扱う体制を整えることで、安心して業務AIの運用が可能です。
継続的なフィードバック分析と精度改善
RAGの運用は一度構築して終わりではなく、継続的な改善が求められます。Difyに搭載されたダッシュボードでは、回答評価やエラーログを可視化でき、改善対象を特定できます。
- 低評価回答の原因を分析
- 問題のあるチャンクを再学習
- 改善後の精度を再検証
PDCAサイクルを継続することで、RAGの品質を段階的に高め、長期的に安定した成果を維持できるでしょう。
まとめ
RAGとDifyを組み合わせたAI運用は、単なる情報検索を超えて、企業知識を資産化する仕組みへと発展しています。精度を支える要素は、チャンク設計・ハイブリッド検索・構造化データ整備に加え、現場主導の更新体制とプロンプトルール設計です。
さらにフィードバック分析を継続することで、精度が時間とともに成長していく仕組みを構築できます。業務課題の可視化からAI活用までを一貫して実現するRAG×Difyは、ビジネスの生産性向上に直結する実践的なAI導入手法といえるでしょう。